
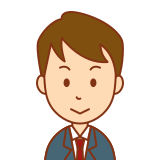
○○万ワードの大口案件があります。量を考慮してディスカウントしてくれませんか?

お断りします。
ボリュームディスカウントについてツイートしたところ多くの反響があったので記事にした。
翻訳業に数量割引は適さない。これはは受け入れてもいけないし、お願いしてもいけない。今回の記事では、これを説明しよう。
ボリュームディスカウントは断るべき理由と、その断り方
フリーランス翻訳者
翻訳会社
ボリュームディスカウントって?

ボリュームディスカウントとは、「大口で発注するから、その分ちょっと安くしてよ」という値切りだ。これは翻訳には適していない。この割引自体が必ずしも悪というわけではない。
遊園地や動物園なのどの有料施設
大量生産できる商品の販売
モバイル通信の契約
これらに共通している点は、割引を提供する側が量を増やしても新しいものを生み出す必要がないことにある。大量生産なら、作る量を増やすだけ。有料施設なら利用者が増えるだけ。回数券なら、多く発行するだけ。
大きな違いは「量が増えると、作業量や労力にそれほど影響がなく、利益が大きく増大する」ことにある。
当然、人間の手による翻訳作業には、これは該当しない。
ボリュームディスカウントがダメな理由
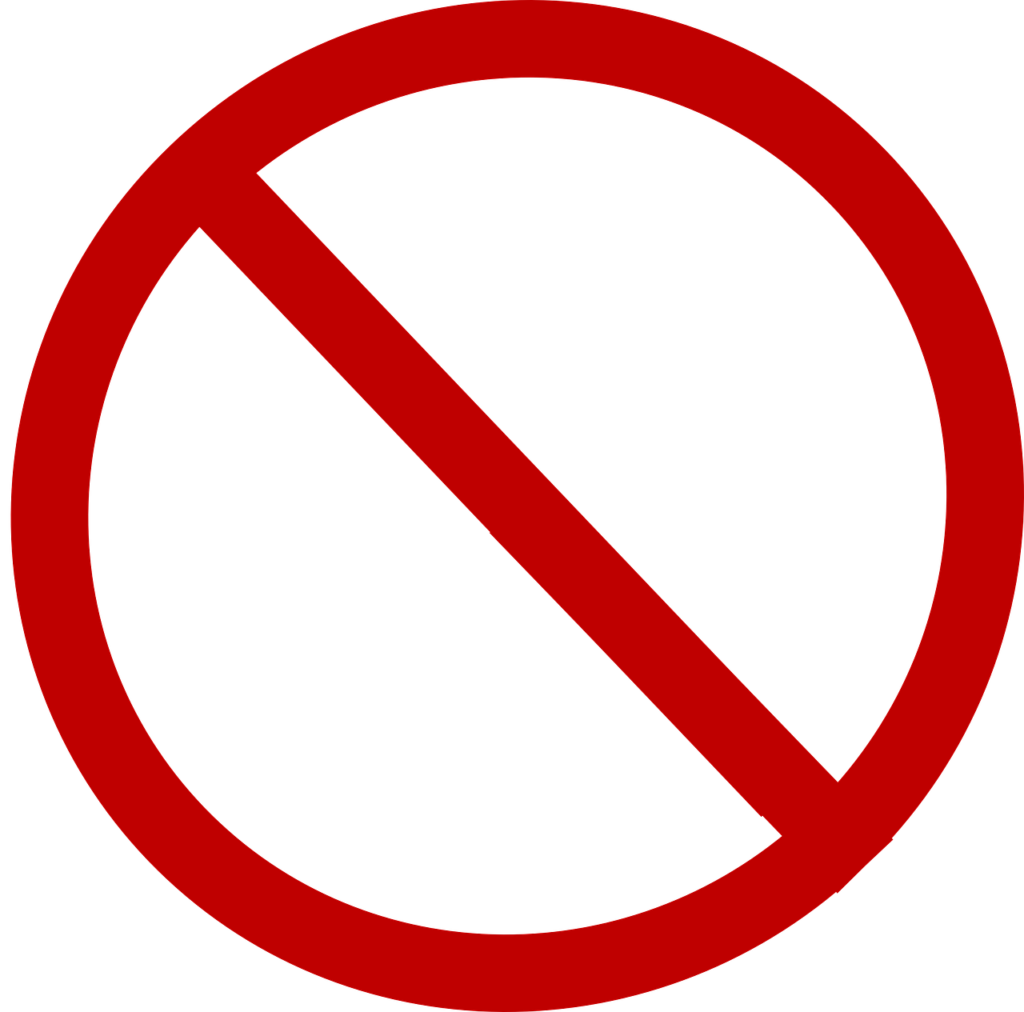
では、なぜこの割引が適切ではないか。
翻訳作業において、量が増えるということは、新しい作業の量が増えるということになる。
大量生産できる商品の数が100個から10,000個に増えるのとはわけが違う。
100ワード終了しても、残りの9,900ワードは全部コピーして行えるわけではない。
普通に考えて100ワードの作業をさらに100倍やることになる。そして、その内容はすべて異なる。
つまり、100ワードに30分かかれば、単純計算で3000分かかることになる。
言ってしまえば、会社員に「残業してね。あーでも、残業したらもっと長く働けるんだから残業代は30%カットね」と言うようなものだ。
翻訳という仕事に「割引を適用せよ」というのは、なんともむちゃくちゃな話だ。
これは出版されている本の値段に似ている。どんなに売れまくっている本でも、印刷本数が多いという理由で安くするという理屈は存在しないはずだ(すなわちボリュームディスカウト)。
大量生産でない翻訳作業に、ボリュームディスカウトを適用するのはむちゃくちゃな話
断り方
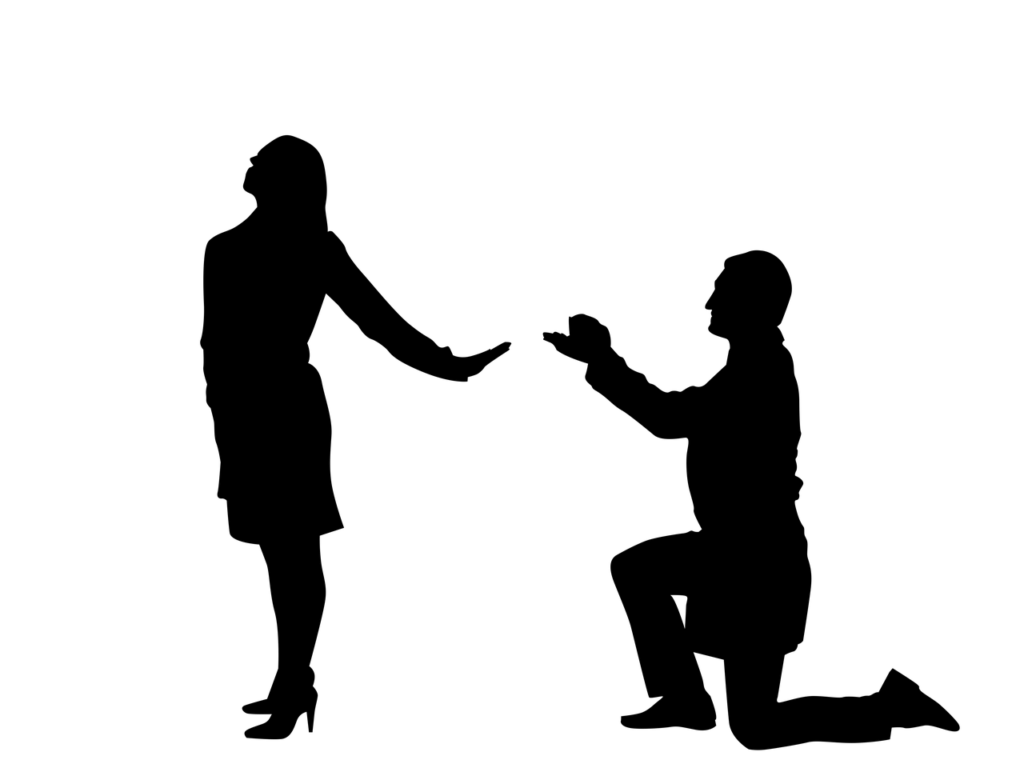
「ボリュームディスカウントは受け入れない」としっかりプロファイルに書くことが大切だ。書かないとしても、契約を行う際に明確に意志を伝えておくと、後にトラブルになりにくい。
中には数量割引が当たり前だと思っているクライアントもいる。
ケンカする必要はないが、理由をしっかり伝えて納得してもらう必要がある。
「100ワードでも、10,000ワードでも、自分ができる最高の仕事を行うようにしています。ボリュームが増えても品質が落ちることはありません。よって、ボリュームが増えても料金が下がるということもありません」。
これだね。
受け入れるべき割引

翻訳にも適用できる割引は存在する。それは翻訳メモリによるマッチ率を使った割引だ。
これは業界では既に当たり前のように行われている。
翻訳メモリを使うことで、既に存在する訳には100%の一致が発生する。これはチェックしくてよいのであれば、そこに料金は発生する必要はない。
100%であっても、内容を確認するのあればレビューのレートを適用すればいい。
また、一部が一致する80%や90%のマッチにも割引きは発生する。
詳しいマッチ率とそのディスカウントについては別の記事でまた説明する。
受け入れるべき割引も存在する。それは100%マッチや部分一致。
ケチになれという意味ではない

ぼくが「こんな割引は受け入れるな」というのは、ケチな翻訳者になれと言っているのではない。
ぼくが言いたいことは「安売りするな」ということだ。
1度割引を受け入れるということは、今後もそれを受け入れていくことになる。それが激化すればするほど、自分の業務がブラック化していく。これはフリーランスにとっては非常に大きな負担となる。
お得意さんのクライアントなら、たまにわずか数十ワードの発注を受けたり、「ちょっとこれ訳してください」と数ワードのものを頼まれることがあるだろう。
そのクライアントとの関係にもよるが、「これくらいなら、無料でいいですよ」と受けてやってもいい。これは信頼関係の上でのみ成立することだが、お互いに助け合うという姿勢は大切だ。
バランスが大切なのは言うまでもない。寛大になるのはよいが、安売りしないことが重要だ。
心を凍らせて冷たくなれという意味ではない。安売りしないということが、長く続けるための鍵となる。
さいごに
翻訳者になりたての頃は、クライアントとのやりとりに色々戸惑うことも多い。安売りしないようにすることが大切だと言ったが、必ずしも状況をつかめるとは限らない。そんなときは、経験のある翻訳者に質問してみるといい。
「こんなときは、どうすればいいの」
ぼくもこういう疑問をいつももっていた。でも質問できる場所があまりなかった。
ぼくでよければ、メールやコメント、お問い合わせから質問してくれてもかまわない。



コメント